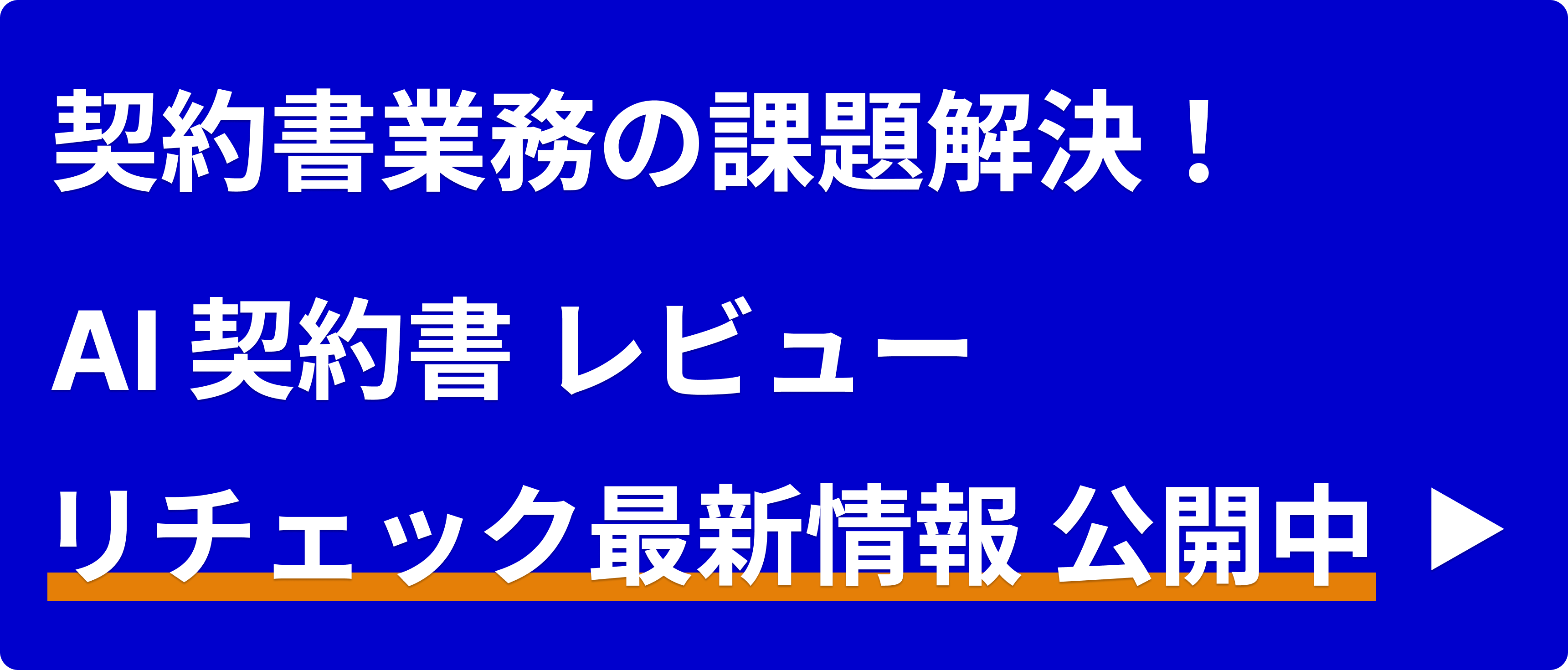COLUMN / SEMINAR
業務委託契約
業務委託契約の概要と書き方、請負型で気をつけるべきポイント
2020.07.29

今回は「業務委託の概要」や「他類型の契約との違い」、「業務委託契約」のうち請負契約の場合の留意点について解説します。

業務委託基本契約書(請負型)の
弁護士監修ひな型
- 「重要箇所」がひと目でわかる、弁護士監修のリスク解説付き
- 相手方からの「自社にとって不利な修正」を予測した対策ガイド付き
<関連記事>契約書チェックをAIで効率化する方法
<関連記事>リーガルチェックとは?契約書チェックの重要性とリスクを解説
業務委託契約とは
まず、民法上「業務委託契約」という類型の契約が定められているわけではありません。
「業務委託契約」とは、その名のとおり、特定の「業務」を第三者に「委託」することを内容とする契約ですが、業務の内容及びその委託の方法如何によって、民法上、「請負契約」又は「準委任契約」に整理されます。
なお、厳密には、「委任契約」とは、委任の対象となる行為が法律行為である場合をいい、「準委任契約」とは、法律行為以外の事実行為を対象とする場合をいいます。
具体的な内容は後述しますが、請負契約と準委任契約では、契約当事者が有する権利義務が民法上異なります。
契約上明記されていない部分は、原則として民法上の定めにより補完されるため、民法上どちらの契約に属するのかという点は重要です。
また、当該契約が「請負契約」であると判断される場合、その契約書は印紙税の対象文書となり、実務上印紙税の要否という点で取扱いが異なることからも、業務委託契約の法的性質を確認することが必要になります。(ただし、電子契約で締結する場合には、印紙税が不要となります。)
以下では、その法的性質が請負契約である業務委託契約を「請負型業務委託契約」、準委任契約である業務委託契約を「準委任型業務委託契約」と呼ぶことにして、説明をします。
業務委託契約書と雇用契約書の違いについて
「雇用契約書」と「業務委託契約書」の違いは、指揮命令に従って業務を提供するかどうかという点です。
「雇用」の場合には、相手方の指揮命令に従って労務を提供する必要があります。
一方、「業務委託」の場合には、仕様等に従う必要はありますが、細かい業務について、自己の裁量で行い、指揮命令を受けないという前提になります。
なお、「雇用契約」の場合、当該契約は労働基準法等の適用を受けることになるというのも、相違点になります。
つまり、主として労働者保護に関する規律(労働時間の管理や解雇の制限等)に服することになります。
「業務委託契約」と「雇用契約」のいずれに該当するかにより、当事者間の権利義務の内容が大きく異なりますし、また、労働基準法等を潜脱する目的で、実態は雇用契約や派遣契約であるにもかかわらず、名目上請負契約である等と偽って、派遣法や労働法の適用を免れる、という、いわゆる偽装請負は社会問題にもなっていたところですので、十分に注意をしなければなりません。
当該契約が「雇用契約」と「業務委託契約」のいずれと評価されるのかという点は、労務の配給を行う者が「労働者」であるか否かによって決定されます。
労働者に該当するかの判断について
この「労働者」に該当するか否かの判断は
- ①労働が他人の指揮監督のもとで行われるか
- ②その対価として賃金が支払われる関係があったことを示す事実関係の有無
に基づいて行われます。
契約書の名称ではなく、その実態を重視して検討されるので注意をしましょう。
具体的には
- ①(a)仕事の依頼、業務従事の指示等に対する許諾の自由の有無、(b)業務遂行上の指揮監督の有無、(c)場所的・時間的拘束性の有無、(d)他の者との労務提供の代替性・専門性の有無
- ②報酬が労務の対価といえるか否か(ちなみに報酬が労務の時間の長さに応じて決まる要素が強いほど対価的要素が強くなり、雇用契約としての色合いが強まります。)といった事実の有無 補完的に
- ③(a)労務提供者が労働者ではない独立の事業者といえるか(機械・器具の負担関係、報酬の多寡等)、(b)特定の企業に対する専属性の程度、(c)選考の過程、公租公課の負担関係等 を加味して判断することになります。
「請負型業務委託契約」と「準委任型業務委託契約」の違いについて
「請負型業務委託契約(請負契約)」と「準委任型業務委託契約(準委任契約)」の大きな違いは、委託された業務について、請負人が、特定の成果物を完成させる義務を負うか否かという点です。
請負契約とは
「請負契約」とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法632条)。
請負型業務委託契約の典型的な例としては、物の製作・加工、建物の設計・建築、物品の郵送、音楽の演奏等が挙げられます。
準委任契約とは
他方、準委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為以外の行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受託者がこれを行うことを約束する契約です(民法643条、656条)。
(なお、法律行為を委託する場合を委託契約といいますが、同じ準則が妥当するため、委任事務の内容が法律行為なのか否かという区別は、そこまで大きな意味を持つところではありせん。)
準委任型業務委託契約は、およそ事務処理が必要になる場面で登場しますが、例えば、医師に診察を依頼する場合、介護サービスを依頼する場合等が挙げられます。
より簡単に書くと、一定の成果を求め、その成果に対して対価を支払うのが「請負契約」、月額や時間に応じた額など、特に成果と連動しない形で報酬が定められている契約が「委任契約」、「準委任契約」となります。
「請負契約」で、請負人及び注文者が負う義務は?
請負人は、注文者に対して契約で引き受けた仕事の完成義務を負います。
目的物の引渡しを必要とする場合には、約束した時期に完成した物を引き渡すことも仕事の完成に含まれます。
他方、注文者は、完成した仕事の結果に対して報酬を支払う義務があります。
この請負の報酬は、契約上特段の定めがない限り、目的物の引渡しが必要な場合には引渡し時に、引渡しが不要な場合には目的物完成時に支払わなければなりません(改正後民法633条)。
また、改正前民法では、契約が途中で解除された場合の報酬の支払いの要否について定めがなかったため、この点が争いになるケースが多々ありました。
そこで、改正後民法では、仕事を完成することができなくなった場合又は請負契約が仕事の完成前に解除された場合について、中途の結果のうち可分な部分によって注文者が利益を受けるときは、その利益の割合に応じて報酬の請求をすることが可能であることが明文化されました(改正後民法634条)。
なお、この点は、契約書で別途の定めを置くことも可能ですので、途中で終了した場合の成果物の引渡や、委託料の支払について、事前に明確に定めておいた方が揉めなくてよいでしょう。
また、請負人は完成した目的物が契約の内容に適合しない場合には、担保責任を負います(改正後民法559条、562条)。
担保責任の内容について
この担保責任の内容について、改正前民法では、注文者は、①修補等の履行の追完、②損害賠償請求、③注文の解除を求めることができるとされていましたが、改正後民法ではこれらに加えて、④代金減額請求もできることが明文化されました。
なお、細かな点にはなりますが、改正前民法では、土地工作物(建物等)の建築請負では、社会経済上の損失の大きさを考慮して深刻な瑕疵があっても注文者は契約を解除することができないとされていましたが(改正前民法635条但書)、この条文は改正後民法では削除されることになりました。
さらに、改正前民法では、注文者が請負人に対して担保責任を追及するためには、原則として目的物の引渡し等から1年以内とされていました。
(但し、例外として建物等の建築請負では引渡しから5年以内、当該建物等が石造、金属造等の場合には引渡しから10年以内に権利行使)。
この点については、瑕疵に気づかず期間が経過してしまうとの批判もあったことから、改正後民法では、契約に適合しないことを知ってから1年以内(但し、引渡から10年以内)にその旨の通知をすれば、請負人の担保責任を追及することができる(ただし、注文者が引渡し時において目的物の不適合につき悪意・重過失の場合を除く。)と変更されました(改正後民法637条)。
例えば、システムに不具合があった場合など、これまでは引き渡しから1年間が担保期間であったところ、10年以内に気が付いて連絡すれば、修正等を修正できるというのが改正後の民法上の規定ということになります。
そのため、それほど長く修繕義務を負いたくないという場合には、システム開発契約等で、別途の合意(1年以内に発見されたバグしか対応しませんと明記するなど)をしておくことが、受託者にとっては非常に重要になってきます。
「準委任型業務委託契約」で、受任者及び委任者が負う義務は?
受任者は、前述のとおり、委任者から委託された行為(委任事務)を行う義務があります。
そして、委任事務の処理を、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって行う義務を負います(善管注意義務、民法644条)。
委任者から請求を受けたときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了したときは、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないとされています(報告義務、民法645条)。
また、委任者は、受任者を信頼してこの人になら任せられると判断して委任事務を委託していると考えられることから、委託された事務の処理について他の者に再委任することは原則として認められません。
改正後民法では、この点が明文化され、受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ更なる受任者(復受任者といいます。)を選任することができない旨明文化されました(改正後民法644条の2)。
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません(民法648条1項)。
履行の途中で委任が終了した場合について
履行の途中で委任が終了した場合については、改正前民法では、受任者に帰責性がない場合に限り、履行の割合に応じて報酬を請求することができるとされていました(改正前民法648条3項)が、仮に受任者に帰責事由があったとしても、既になされた委任事務の履行に対しては履行の割合に応じて報酬を請求できるとするのが合理的であることから、改正後民法648条3項において、委任者に帰責性のない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合(なお委任者に帰責性がある場合には、報酬全額の請求が可能です。)又は委任が履行の途中で終了した場合には、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができると変更されました(改正後民法648条3項)。
特定の成果に対して報酬を支払う旨の合意がされた場合について
また、特定の成果に対して報酬を支払う旨の合意がされた場合については、引渡しが必要なときには、報酬の支払いと同時履行の関係にたつことを明示した上で、成果が得られる前に、委任者に帰責性のない事由によって委任事務の履行ができなくなった場合(なお委任者に帰責性がある場合には、報酬全額の請求が可能です。)又は成果が得られる前に委任契約が解除された場合において、既に履行した委任事務の結果が可分でその部分によって委任者が利益を受けるときは、受任者は、その利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされました(改正後民法648条の2第2項、634条)。
以上が「業務委託契約」の大枠となります。
業務委託契約(請負型)で気を付けるべきポイントは?
請負型の業務委託契約では、受託者は、委託された業務について、請負人が、特定の成果物を完成させる義務を負います。
具体的には、建物の建築請負契約であれば、建物を完成させることとの対価として、請負代金を受領します。
システム開発契約でも、請負型の場合、単に見積もった工数の人員を投入するだけではなく、一定のシステムを完成までさせる義務を負います。
そのため、請負型の業務委託契約を作成する際、および、レビューする際に気を付けるべきポイントとしては、
- ① 完成させなければならない委託業務(システムや建築物など)について、後の争いが生じないように詳細に疑義が生じないように規定すること
- ② 委託業務が完成したかの確認方法について明確に定めること(検収について適切に定めること)
- ③ 検収で不合格になった場合の対応方法について定めておくこと
- ④ 検収で見つけられないような問題点があった場合、いつまでの期間どのように対応するか定めておくこと(従前の瑕疵担保責任、2020年4月の民法改正以降は契約不適合責任)
- ⑤ 納期までに完成できなかった場合について、どのように対応するかを定めておくこと
- ⑥ 完成前に契約が終了した場合に、未完成の成果物の取扱いについて定めておくこと
- ⑦ 成果物についての権利の帰属を明確に定めておくこと
- ⑧ 債務不履行(納期遅延、契約不適合があった場合など)の場合の損害賠償の範囲
といった点が挙げられます。
業務範囲を定める
まず、【① 完成させなければならない委託業務(システムや建築物など)について、後の争いが生じないように詳細に疑義が生じないように規定すること】ですが、例えばシステム開発契約では、この点で揉める例も多いですが、システム開発のプロセスは、大まかに企画・要件定義段階、開発段階、運用段階に分類されます。
個々の事例においては、例えば要件定義については既に委託者の方で確定させているため、基本契約の対象外ということもあり得るでしょうし、また、ソフトウェアの運用準備・移行までは委託業務に含まれず、ソフトウェアの開発(設計、プログラミング、テスト)までで業務終了という場合もあり得ます。それぞれのケースに合わせて、適切な業務の範囲を規定する必要があります。
なお、この①に関連する問題として、「仕様変更となって追加報酬が発生するのか」、「当初の業務の範囲内の作業なのか」もよく出てくる点です。この点も、結局、当初の業務範囲を明確にしておくことと、業務の範囲を超えた作業が発生した時点で、追加報酬について明確に定めることなく作業を進めるのではなく、まず、追加報酬について議論して定めておくことが重要となります。
【PRリンク】面倒な契約書チェックがクラウドAIならあっという間に完了します
検収方法を定める
次に【② 委託業務が完成したかの確認方法について明確に定めること(検収について適切に定めること)】ですが、ここも、「何をもって完成とするのか」、「どういった内容のテストを何回、誰がして、どのような結果を出せば検収合格とするのか」、が後々大問題になるようなケースもあります。
対象となる委託業務の種類等によって、検収の重要性やポイントは異なってきますので、同種のサービスなどの委託事例における検収の方法等を参考に、事前に慎重に定めておく必要があります。
検収不合格の場合の対応
【③ 検収で不合格になった場合の対応方法について定めておくこと】ですが、これは【② 委託業務が完成したかの確認方法について明確に定めること(検収について適切に定めること)】とセットで定められていることも多いです。
検収をやってみたところ結果が不合格となった場合に、対象業務によりますが、再度作り直すのか、不具合があったところを直すのか、直すにしてもやり方などは受託者側で決めてよいのか、委託者の方でやり方など指示できるのか、できていない箇所だけ返金(減額)対応するのか、などです。
「委託者の指示に従い不具合箇所を直さなければならない」とされている場合、いくら人員工数や費用がかかってもとにかく直すとなると、受託者として想定外の人員工数を割く必要が生じたり、費用がかかったりするリスクがあります。
一方委託者側として、性能が100%出ないと意味がないという場合には、性能90%の成果物を納入されて、10%の減額を受けたとしても、そもそもそのような成果物は全く意味がなく、いらないという場合もあり得ます。
そのため、検収の規定(上記②)と同様に、実際に検収不合格の場合に、どのような対応が可能か、どのような対応をしてもらう必要があるのかを慎重に検討して、事前に定めておく必要があります。
請負の契約不適合責任
【④ 検収で見つけられないような問題点があった場合、いつまでの期間どのように対応するか定めておくこと(従前の瑕疵担保責任、2020年4月の民法改正以降は契約不適合責任)】は、検収で見つからなかったような隠れた問題点があった場合に、いつまでの期間、どのような対応をするかを定めておくという点です。
ここも、③の場合と同様、不具合があったところを直すのか、直すにしてもやり方などは受託者側で決めてよいのか、委託者の方でやり方など指示できるのか、できていない箇所だけ返金(減額)対応するのか、などが問題になります。
③と同様に、実際に隠れた問題点が保証期間内に発覚した場合に、「どのような対応が可能か」、「どのような対応をしてもらう必要があるのか」を慎重に検討して、事前に定めておく必要があります。
なお、【保証期間(契約不適合責任を負う期間)】ですが、前回のコラムでも書きましたが、ここは、改正民法により変更があった個所になります。
改正前民法では、「注文者が請負人に対して担保責任を追及するためには、原則として目的物の引渡し等から1年以内、例外として建物等の建築請負では引渡しから5年以内、当該建物等が石造、金属造等の場合には引渡しから10年以内に権利行使をしなければならない」とされていました。
この点について、新民法では、「契約に適合しないことを知ってから1年以内(但し、引渡から10年以内)にその旨の通知をすれば、請負人の担保責任を追及することができる(ただし、注文者が引渡し時において目的物の不適合につき悪意・重過失の場合を除く。)」と変更されました。
例えば、システムに不具合があった場合など、これまでは、特に契約書に規定がなかった場合でも、引き渡しから1年間が担保期間であったのですが、今後は、10年以内に気が付いて連絡すれば、修正等を修正できることとなったのです。
但し、この、契約不適合責任を負う期間は、当事者間で別途の合意をすれば民法の適用はありませんので、それほど長く修繕義務を負いたくないという場合には、システム開発契約等で、別途の合意(1年以内に発見されたバグしか対応しませんと明記するなど)をしておくことが、受託者にとっては非常に重要です。
【PRリンク】面倒な契約書チェックがクラウドAIならあっという間に完了します
納期遅延の場合の責任
【⑤ 納期までに完成できなかった場合について、どのように対応するかを定めておくこと】の納期遅延ですが、納期を少しでも遅れた場合に無意味になるような特殊な事情がある場合には(例えば、クリスマスケーキをクリスマス当日までに納入する契約など。)、納期遅延で納入された場合に委託者側で一切の支払義務を負わないように、その場合には直ちに契約を解除可能で、解除された場合に委託者が一切の支払義務を負わない旨明記されている場合があります。
ただ、納期遅延した場合に、履行が無意味にまではならないものの、納期が遅延すると非常に大きな損害が生じることが予想される場合には(例えば、複雑なシステムのほんの一部だけを請け負っていたところ、当該一部だけが遅れ、予定されていたサービス提供が大幅に遅れた場合など。)、納期が遅れた場合について、1日当たりの違約金を定めておくような例もあります。
受託者としては、そのような規定が入ってしまった場合、遅延させないように努めたとしても、予定外の事態が生じ遅延が生じることはありえ、その場合、遅延日数が積みあがって、大きな金額の違約金の支払い義務を負う場合もあり得ます。
但し、納入遅延について違約金まで定めている例は多数ではなく、納入遅延が生じそうになった場合には速やかに委託者に連絡し、対応について協議することとし、更に、通常の損害賠償の範囲で、委託者が納入遅延について実際に生じた損害を立証した範囲で支払うというのが一般的な規定にはなっているようには思います。
途中終了の場合の成果物の取扱いと支払
【⑥ 完成前に契約が終了した場合に、未完成の成果物の取扱いについて定めておくこと】ですが、これは、何らかの理由で業務委託契約が途中終了した場合に、完成前のシステム等をどう扱うかの問題です。
受託者側で持っていても意味がない場合が多いため、一般的に、完成前であっても委託者に引き渡すこととしている例が多いようです。その場合の支払ですが、受託者としては、完成している割合に従って支払いを受けたいところです。使った分の人員工数や費用を取り戻すためです。
一方、委託者としては、完成前に引き渡しを受けると、これを別の業者に依頼するなどして完成させる必要があることになりますが、割合的に支払っても、残りの残額で、残作業を別業者に依頼することは難しい場合も多いようです。
そのため、委託者としては、完成前の引渡しにより利益を受けた範囲においてのみ支払うとする方が有利です。つまり、一から他の業者に依頼するよりも安くなった分のみを途中まで完成させた受託者に支払うという規定です。
最後に⑦、⑧ですが、これは、準委任の場合とも共通しますので、次回詳細に記載したいと思います。
【PRリンク】面倒な契約書チェックがクラウドAIならあっという間に完了します

業務委託基本契約書(請負型)の
弁護士監修ひな型
- 「重要箇所」がひと目でわかる、弁護士監修のリスク解説付き
- 相手方からの「自社にとって不利な修正」を予測した対策ガイド付き
<関連記事>契約書チェックをAIで効率化する方法
<関連記事>リーガルチェックとは?契約書チェックの重要性とリスクを解説

株式会社リセ
株式会社リセは、西村あさひ法律事務所出身の代表が設立し「争いのない『滑らかな』企業活動の実現」をミッションに掲げています。
専門弁護士の知見と最先端技術を組み合わせ、企業法務や弁護士の業務効率化を支援し質の向上が可能な、
AI契約書レビューサービス「LeCHECK」、翻訳機能サービス「LeTRANSLATE」、契約書のAI自動管理サービス「LeFILING」 を提供しています。



 人気記事ランキング
人気記事ランキング


 カテゴリー
カテゴリー






 LIST
LIST