COLUMN / SEMINAR
リーガルチェック
弁護士の契約書リーガルチェックと社内チェックの違い 〜AIツールで効率化する最新手法も紹介〜
2025.05.20
この記事のまとめ
この記事では、契約書のリーガルチェックにおける「弁護士依頼」と「社内対応」のメリットと課題を解説しています。
弁護士依頼はリスクを抑えることが可能ですが費用や時間がかかる場合もあり、社内対応は属人化やナレッジ不足の問題があります。
そこで、弁護士監修による品質とAIによる効率化を両立する、
AI契約書レビューツール「リチェック」をご紹介。
専門知識がなくても使いやすく、法務業務の負担を軽減し、リスク管理を支援します。
契約書のリーガルチェックを行う際、多くの企業が「弁護士に依頼するか」「社内で対応するか」の判断に悩みます。
弁護士に依頼すれば専門的な視点でのリスク対応が可能な一方、費用ややり取りの手間が気になるという声も少なくありません。一方で、社内で対応する場合には、限られたリソースのなかで法務部門が判断や調整を重ねる必要があり、属人化やナレッジの蓄積といった課題にも直面します。
本コンテンツでは、リーガルチェックを「弁護士に依頼する場合」と「社内で対応する場合」の両面から、具体的な流れや費用感、対応時の注意点を解説します。
自社の体制や契約リスクのレベルに応じて、より効果的で無理のない対応方法を選ぶための参考として、ぜひご活用ください。

株式会社リセ
株式会社リセは、西村あさひ法律事務所出身の代表が設立し「争いのない『滑らかな』企業活動の実現」をミッションに掲げています。
専門弁護士の知見と最先端技術を組み合わせ、企業法務や弁護士の業務効率化を支援し質の向上が可能な、
AI契約書レビューサービス「LeCHECK」、翻訳機能サービス「LeTRANSLATE」、契約書のAI自動管理サービス「LeFILING」 を提供しています。
-
リーガルチェックに関する資料を無料配布中
- 「法務の未来がわかる リーガルテック入門ガイドブック」
- 「契約の立場ごとに学ぶ AI契約書レビュー支援ツール活用ガイド」
- 「「法改正に追いつけない」「専門知識が足りない」 法務部門が直面する壁を超えるには」
お持ちの契約書で、弁護士監修のAIリーガルチェックサービス「リチェック」を試してみませんか?
<関連記事>【2025年最新】契約書のリーガルチェックとは?社内対応・AI活用まで徹底解説
弁護士にリーガルチェックを依頼する場合の費用や流れを解説
1.目的の明確化と事前準備
リーガルチェックを弁護士に依頼する際は、まず自社が契約書のどの部分にリスクを感じているのか、またはどのような点を重視しているのかといった目的や期待する成果を明確にすることが重要です。
加えて、契約の背景や取引の経緯、自社の事業内容や過去の類似事例、取引条件などの関連資料を整理しておきます。
必要に応じて社内で一次的なチェックを行い、疑問点やリスクを洗い出しておくことで、弁護士への説明や依頼がより円滑になります。
2.弁護士の選定
次に、依頼内容に適した専門分野や経験を持つ弁護士や法律事務所を選定します。
信頼性や過去の実績、専門性を確認することがポイントです。
もし顧問弁護士がいる場合は、まず顧問弁護士に相談するのが一般的であり、顧問契約がない場合は複数の法律事務所から見積もりを取り比較検討することも有効です。
3.依頼内容の説明・相談
弁護士に依頼する際は、チェックしてほしい契約書や関連資料を提出し、契約の目的や回避したいリスク、希望する修正方針などを具体的に説明します。
また、会社の事業内容や資本金、従業員数などの基本情報も共有することで、弁護士が自社の状況を正確に把握し、より適切な法的アドバイスを提供しやすくなります。
4.見積もりの取得と契約締結
弁護士から費用や納期の見積もりを受け取り、その内容に納得した場合は正式に依頼契約を締結します。
費用や対応範囲、納期については事前にしっかり確認し、必要があれば複数の事務所を比較することが推奨されます。
5.リーガルチェックの実施とフィードバック
弁護士は提出された契約書を精査し、法的な問題点や修正案を提示します。
必要に応じて追加説明や再修正の依頼を行い、双方で内容を詰めていきます。
弁護士からのフィードバックをもとに契約書の修正を進めることで、リスクの低減や自社の利益確保につながります。
6.完了・納品
最終的に弁護士からチェック結果や修正済みの契約書が納品されます。
内容に不備がなければ、これでリーガルチェックは完了となります。必要に応じて、弁護士からのアドバイスをもとに契約交渉や締結手続きへと進みます。
費用の相場とポイント
| 契約書の種類・内容 | 費用相場(目安) |
|---|---|
| シンプル・定型的な契約書 | 1~5万円 |
| 一般的な取引契約書 | 5~15万円 |
| 複雑・非定型的な契約書 | 10~20万円以上 |
| 高度な専門性・国際契約書 | 20万円以上 |
| 顧問契約(月額) | 3~5万円 |
| 相談料(初回等) | 30分5,000円~1万円 |
※費用は契約書の分量、難易度、弁護士の専門性や経験、地域(都市部は高額傾向)、事務所の規模などで変動します。
※顧問契約を結んでいる場合、月額顧問料の範囲内で対応してもらえるケースが多く、個別依頼よりコストを抑えられることがあります。
社内でリーガルチェックを実施する場合の流れを解説(受け手の場合)
次に、社内で実施する場合の流れを、それぞれ契約の立場別に解説します。
1. 契約書の受領と状況把握
契約書のドラフトは、営業部門や事業部門など、契約の「出し手」から、メールや社内システム経由で法務部門に送付されます。
法務担当者はまず、その契約書の送付目的や背景、締結の緊急度、相手方企業名、契約類型(業務委託・秘密保持など)といった情報を確認します。
同時に、関係部署にヒアリングを行い、業務実態や契約リスクの所在についての前提理解を深めます。
ここで情報が不足している場合は、再度「出し手」に確認を取ることになり、確認作業が往復することも少なくありません。
2. 契約書レビューの着手
事前情報を踏まえて、法務担当者は契約書本文のレビューに取り掛かります。
まずは条文の構成や条項の網羅性、抜け漏れがないかを確認し、次に自社の立場から不利な条件やリスクが含まれていないかを精査します。
リスクの洗い出しにあたっては、過去の契約例や自分の経験をもとに判断することが多く、過去のファイルを探したり、以前の担当者に聞いたりする場面もあります。
会社としての判断方針が明文化されていない場合は、判断に迷いが生じることもあり、上司への確認や相談に時間を要することもあります。
3. 修正案の作成と関係者への確認
リスクのある条文を特定した後、法務担当者は具体的な修正案を検討します。
過去に使われた表現や、他社との類似案件を参考にしながら文言を作成するケースが多く、判断に迷うポイントについては、他の法務メンバーとディスカッションを行うこともあります。
特に重要な契約や新しい類型の契約では、上司や部長レベルの承認が必要になることもあり、確認プロセスに時間がかかることがあります。
場合によっては、経営層や関連部署へのリスク報告も求められ、調整・合意形成に一定の手間を要します。
4. 修正文案の送付と先方との折衝
社内での確認が終わると、法務部門から「出し手」に対して修正案を返送し、取引先への送付が行われます。
ここで先方から再度修正やコメントが戻ってくると、再レビューが必要になります。
折衝の内容が複雑だったり、先方の提示する表現が新規性の高いものであったりする場合、再度法務部門内での検討や上長判断が必要になることもあります。
こうした往復が複数回発生すると、契約締結までに大きなタイムロスが生じることもあります。
5. 契約締結とナレッジ蓄積
最終的に合意に至った契約書は、紙または電子契約で締結されますが、その後のナレッジ蓄積は必ずしも仕組み化されておらず、レビュー時の判断理由や修正履歴が個人の手元にしか残らないことも多々あります。
情報がファイルサーバーやメールボックスに点在しているため、後から同様の契約書をレビューする際に過去の経緯をたどるのが困難になることもあります。
結果として、同じような検討を何度も繰り返す属人化のループが生まれ、業務効率や判断の一貫性に課題を残す状況となっています。
社内でリーガルチェックを実施する場合の流れを解説(出し手の場合)
1. 担当から作成依頼
契約書の作成依頼は、口頭、メール、あるいはSlackなどのチャットツールで行われます。
依頼者が自らドラフトを添付する場合もありますが、多くの場合は、「こういう契約が必要」といったざっくりした依頼が来るだけで、具体的な条件や背景情報が不足していることが少なくありません。
そのため、まずは契約の目的や相手方との関係性、スケジュール感など、必要な情報をこちらから積極的にヒアリングすることが求められます。
2. 前提社内ヒアリング
契約書の正確な作成のためには、事前の社内ヒアリングが不可欠です。
取引の概要、相手方の立場、契約対象の金額・期間・成果物など、確認すべきポイントはあらかじめリスト化しておくと便利です。
ヒアリングはメールで済ませるケースもありますが、背景事情やニュアンスを把握するには、電話や対面でのコミュニケーションが望ましいとされています。
これにより、契約書に盛り込むべき重要事項を漏れなく把握できます。
3. 契約書の作成
ヒアリングした情報をもとに、契約書をゼロから、または自社のひな型をベースに作成します。
ローカルフォルダや共有ドライブから過去の契約書を探し出し、似た事例を参考にしながら修正を加えて作成していく必要があります。
複数の過去事例を横断的に比較するには時間がかかり、重要条文の表現や過去の交渉履歴などを都度確認する必要も出てきます。
4. 内容の最終チェック
自分で作成した契約書を見直す際には、漏れや表現の揺れがないか、自社の基準に沿っているか、法務部門からの過去の指摘事項が反映されているかなど、複数の観点からチェックを行う必要があります。
重要な契約や複雑な契約の場合は、同じ契約類型の他のひな型とも比較しながら、リスクの見落としがないか注意を払います。
5. 最後に形式チェック
契約条文を加筆・修正した結果、条番号がずれていたり、条文の相互参照が不正確になっていることがあります。
Wordのナビゲーションや検索機能などを活用して、手作業で確認することになります。
表記揺れや全角・半角の混在など、細かな表記ミスも手動で確認する必要があり、かなりの集中力が求められます。
6. 社内提出
完成した契約書を、作成を依頼した担当者にメールなどで提出します。
その際には、条文ごとの意図や留意点などを添えておくと、後々の説明やトラブル防止にも役立ちます。
ただし、こうした情報共有が曖昧だったり、言った言わない問題が起きるリスクもあるため、できる限り記録として残る形で残しておくのが理想です。
7. 相手方にフィードバックし、コメントが入った場合
相手方から修正が返ってきた場合には、まずどのような意図で修正されているかを確認します。
交渉担当者を通じて、相手の背景や温度感を探り、どこまで譲歩するか、どこは絶対に譲れないのかなどを社内で再調整します。
このプロセスでは、過去の対応実績を思い出しながら、「前はここまでOKにした」「この会社にはこのリスクを飲んだ」などの知見を反映させる必要があります。
ナレッジの属人化が起きやすく、経験の浅いメンバーには難易度が高い場面です。
8. 最終版についての連絡・確認
相手方との合意が取れたら、最終版の契約書を確認し、修正が必要な箇所がないかをチェックします。
特に、相手方が手を入れた箇所以外に変更が加えられていないかは、Wordの「文書比較」機能を使って確認するのが一般的です。
最終確認後、契約書ファイルを社内の共有フォルダやクラウドストレージに保存し、必要に応じて紙で印刷・押印手続きを行います。
このように、契約書の作成・チェック業務は、ヒアリングから作成、修正対応、形式チェックに至るまで、担当者の経験と集中力に大きく依存します。
作業時間や確認漏れリスクを最小限に抑えるには、属人的なナレッジをチーム内でしっかり共有する体制が不可欠です。
弁護士に依頼する場合・社内で対応する場合のメリットとデメリットまとめ
弁護士に依頼するメリット・デメリット
メリット:
- リスクを抑えられ、トラブルを未然に回避できる
- 契約後のフォローを依頼できる
デメリット:
- 顧問契約をしていない場合、都度費用が発生する
- 顧問契約の場合も、顧問料で対応できる範囲には制限がある
- 修正を繰り返していると、時間が長くかかってしまう場合も
社内対応のメリット・デメリット
メリット:
- 外注費用を抑えられる
デメリット:
- 属人化しやすく、法務初心者の場合リスクのある契約をしてしまう可能性がある
- 社内のリソースが不足している場合、時間が長くかかる
- 法改正など最新情報キャッチアップの難易度が高い
弁護士に依頼する方法と社内対応、それぞれにメリット・デメリットがあります。
リスクを最小限に抑えたい場合や契約後のフォローを重視するなら弁護士依頼が安心ですが、コストや時間面での負担も無視できません。
一方で、社内対応はコストを抑えられる反面、法務リソースの不足や最新情報の追随が難しく、見落としによるリスクも伴います。
AI契約書レビューツール「リチェック」なら、内製と外注それぞれの利点を両立できます
これまでご紹介してきたように、弁護士に契約書レビューを依頼する場合は「安心感」や「高度な専門性」といった利点がある一方で、費用や対応スピードの観点で導入のハードルが高くなりがちです。
一方、社内で対応する場合はコストを抑えられる反面、知識の属人化、判断のばらつき、情報収集の負担といった課題が避けられません。
こうした両者の特長を効果的に組み合わせ、安心感と効率性を両立できる新しい選択肢が、AI契約書レビューツール「リチェック」です。

弁護士の知見を標準装備
20名以上の弁護士チームが監修し、契約書類型ごとの注意点や修正文例、参考条文を豊富に収録。
条文ごとに「なぜこのリスクがあるのか」「どんな修正が望ましいか」を丁寧に解説しており、専門家の判断基準に基づいてレビューできます。
弁護士監修の契約書ひな形もご提供
契約書をゼロから作成する場面でも、弁護士監修の高品質なひな型を立場別にご用意。
自社の契約方針に合った条文をベースにでき、初期段階からリスクを抑えた契約書作成が可能です。
AIによる迅速な条文解析で業務を効率化
契約書をアップロードするだけで、AIが条項を解析し、欠落リスク・要注意条文・立場に応じた代替案を提示。
チェックの見落としを防ぎつつ、短時間で高品質なレビューを実現します。
法務のリソース不足もカバー
一人法務や経験の浅いメンバーでも、専門弁護士の知見に基づいたレビューを効率よく進められるため、属人化の解消やナレッジの平準化にもつながります。
弁護士の専門知とAIの処理速度を組み合わせることで、これまで手間のかかっていたリーガルチェック業務が飛躍的に効率化されます。 法務部門の負荷軽減とリスク管理の高度化を同時に実現する支援ツールです。
この記事のまとめ
この記事では、契約書のリーガルチェックを「弁護士に依頼する場合」と「社内で対応する場合」のそれぞれの特徴やメリット・課題を詳しく解説しました。
弁護士に依頼すると専門的な法的リスクの検証が可能ですが、費用や対応時間の面で負担がかかることがあります。一方、社内チェックはスピーディーに対応できる反面、属人化やナレッジ不足によるリスクが残る場合も少なくありません。
そんな中で、新たな選択肢として弁護士の専門知識をベースにしつつAIの力で効率化を実現する契約書レビューツール「リチェック」をご紹介しました。専門知識がない方でも使いやすく、法務業務の負担軽減とリスク管理の両立を支援する製品です。
契約書リーガルチェックの課題解決や効率化をお考えの方は、ぜひ下記の製品ページをご覧ください。
-
リーガルチェックに関する資料を無料配布中
- 「法務の未来がわかる リーガルテック入門ガイドブック」
- 「契約の立場ごとに学ぶ AI契約書レビュー支援ツール活用ガイド」
- 「「法改正に追いつけない」「専門知識が足りない」 法務部門が直面する壁を超えるには」
お持ちの契約書で、弁護士監修のAIリーガルチェックサービス「リチェック」を試してみませんか?

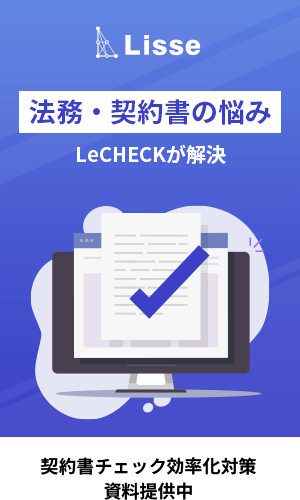

 人気記事ランキング
人気記事ランキング



 カテゴリー
カテゴリー






 LIST
LIST